混合液と純物質
Point1 混合物と純物質
たとえば、空気はいくつもの物質が合わさって構成されています。
空気に含まれる成分(体積%)
窒素:78.08
酸素:20.95
Ar :0.93
CO2:0.033
etc…
同じように、海水もいくつもの物質が合わさって構成されています。
海水100g中に溶けている物質(g)
塩化ナトリウム :2.72
塩化マグネシウム :0.38
硫酸マグネシウム :0.17
硫酸カルシウム :0.13
硫酸カリウム :0.09
炭酸カルシウム :0.01
また、海水はろ過や蒸留を行うことで2種類以上の物質に分離させることができます。
(例)蒸留(テスト出る!!!)
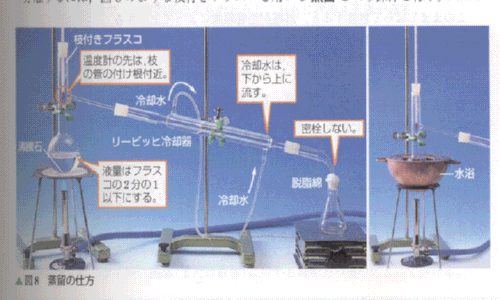
このように、ろ過や蒸留などで2種類以上の物質に分離することができる物質を混合物といいます。つまり、海水は混合物であるといえます。海水だけでなく、自然界の物質はほとんどが混合物なのです。
また、水や塩化ナトリウムなどは、ろ過や蒸留といった、物理的方法ではこれ以上細かく他の物質に分離させることができません。
このように、1種類の単体、または1種類の化合物からなる物質を純物質といい、それぞれの物質に固有の性質をもっています。
たとえば、融点・沸点は物質によって異なるので、それらの温度を調べることによってその物質が何であるかを特定することができます。
ここで、 中学校の内容をおさらいします。
単体と化合物
1種類の元素からできている物質を単体という。
2種類以上の元素からできている物質を化合物という。
(例)
①単体…水素、臭素、亜鉛など
②化合物…水、アンモニア、塩化ナトリウムなど
純物質と単体を間違える、化合物と混合物の区別がつかない人は↓
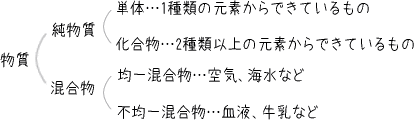
混合物…物理的方法で分けられる。
化合物…化学的方法で分けられる。
B混合物の分離
ろ過
ろ紙の目を通過できるかどうかで物質を分離する…固形成分を分離できる。
蒸留
混合物中の成分物質の沸点の差を利用して分離する。
分留
適当な温度範囲に分けて蒸留を行う。
その他再結晶、昇華法、抽出、クロマトグラフィーがある。(詳しくは教科書参照)
たとえば、空気はいくつもの物質が合わさって構成されています。
空気に含まれる成分(体積%)
窒素:78.08
酸素:20.95
Ar :0.93
CO2:0.033
etc…
同じように、海水もいくつもの物質が合わさって構成されています。
海水100g中に溶けている物質(g)
塩化ナトリウム :2.72
塩化マグネシウム :0.38
硫酸マグネシウム :0.17
硫酸カルシウム :0.13
硫酸カリウム :0.09
炭酸カルシウム :0.01
また、海水はろ過や蒸留を行うことで2種類以上の物質に分離させることができます。
(例)蒸留(テスト出る!!!)
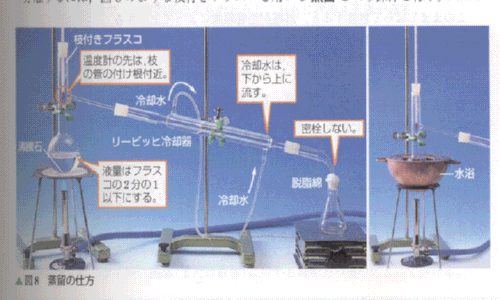
このように、ろ過や蒸留などで2種類以上の物質に分離することができる物質を混合物といいます。つまり、海水は混合物であるといえます。海水だけでなく、自然界の物質はほとんどが混合物なのです。
また、水や塩化ナトリウムなどは、ろ過や蒸留といった、物理的方法ではこれ以上細かく他の物質に分離させることができません。
このように、1種類の単体、または1種類の化合物からなる物質を純物質といい、それぞれの物質に固有の性質をもっています。
たとえば、融点・沸点は物質によって異なるので、それらの温度を調べることによってその物質が何であるかを特定することができます。
| 物質 | 融点[℃] | 沸点[℃] | 密度(0℃)[g/cm3] |
| 窒素 | -210 | -196 | 0.00125(気体) |
| 酸素 | -218 | -183 | 0.00143(気体) |
| 水 | 0.00 | 100 | 1.00(液体) |
| 塩化ナトリウム | 801 | 1413 | 2.17(固体) |
ここで、 中学校の内容をおさらいします。
単体と化合物
1種類の元素からできている物質を単体という。
2種類以上の元素からできている物質を化合物という。
(例)
①単体…水素、臭素、亜鉛など
②化合物…水、アンモニア、塩化ナトリウムなど
純物質と単体を間違える、化合物と混合物の区別がつかない人は↓
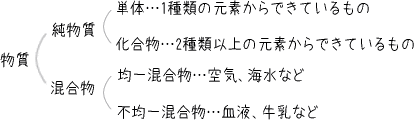
混合物…物理的方法で分けられる。
化合物…化学的方法で分けられる。
B
ろ過
ろ紙の目を通過できるかどうかで物質を分離する…固形成分を分離できる。
蒸留
混合物中の成分物質の沸点の差を利用して分離する。
分留
適当な温度範囲に分けて蒸留を行う。
その他再結晶、昇華法、抽出、クロマトグラフィーがある。(詳しくは教科書参照)
br→
main_box